イベントスケジュール
-
- 説明会・体験会
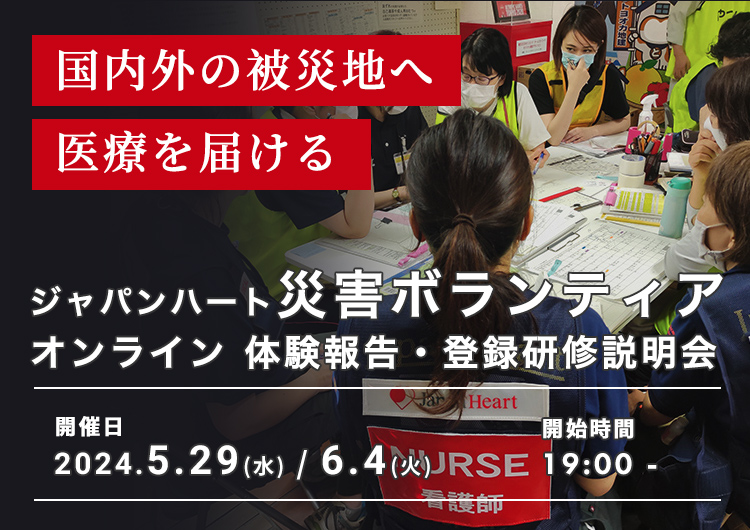
- 05/29 ~ 06/04
- オンライン
- 【iER】災害ボランティア – 体験報告・登録研修説明会
- 募集中 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 06/12
- オンライン
- 2024年度 スマイルスマイルプロジェクト サポーター登録説明会開催のお知らせ
- 受付中 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 06/22
- 東京・オンライン
- 【看護師・助産師向け】ジャパンハート募集説明会(オンライン) ~国際医療×離島・へき地医療~
- 受付募集中 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会
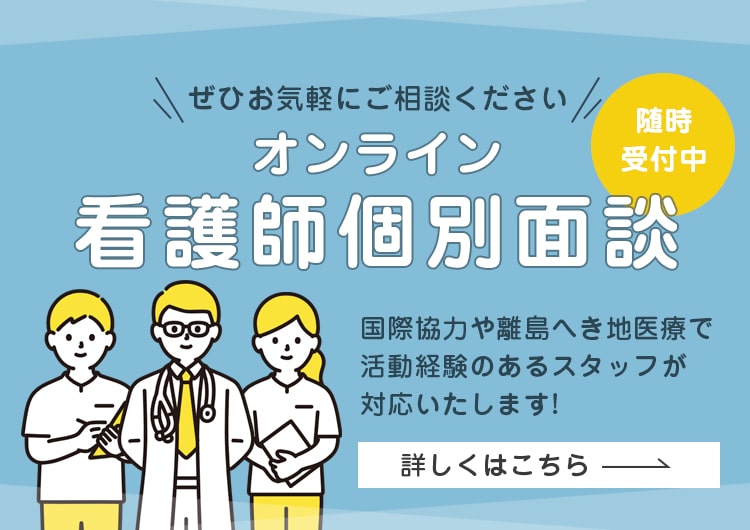
- 04/01 ~ 07/31
- オンライン
- オンライン看護師個別面談~国際協力や離島へき地医療で活動経験のあるジャパンハートスタッフが対応します~
- 募集中 More info
- 説明会・体験会
-
- 講演

- 01/20
- オンライン
- 【令和6年能登半島地震】緊急報告会
- アーカイブ公開中 More info
- 講演
-
- 講演

- 04/12
- 東京
- 『NGOで働くとは』- LIFULL One P’s Night にカンボジアこども医療センター 小林が登壇!
- 受付中 More info
- 講演
-
- ボランティア・ツアー

- 03/02 ~ 06/30
- 海外
- 【5月受付開始】看護師・助産師向けツアー:カンボジア 臨床医療を知る
- 募集中 More info
- ボランティア・ツアー
-
- 説明会・体験会
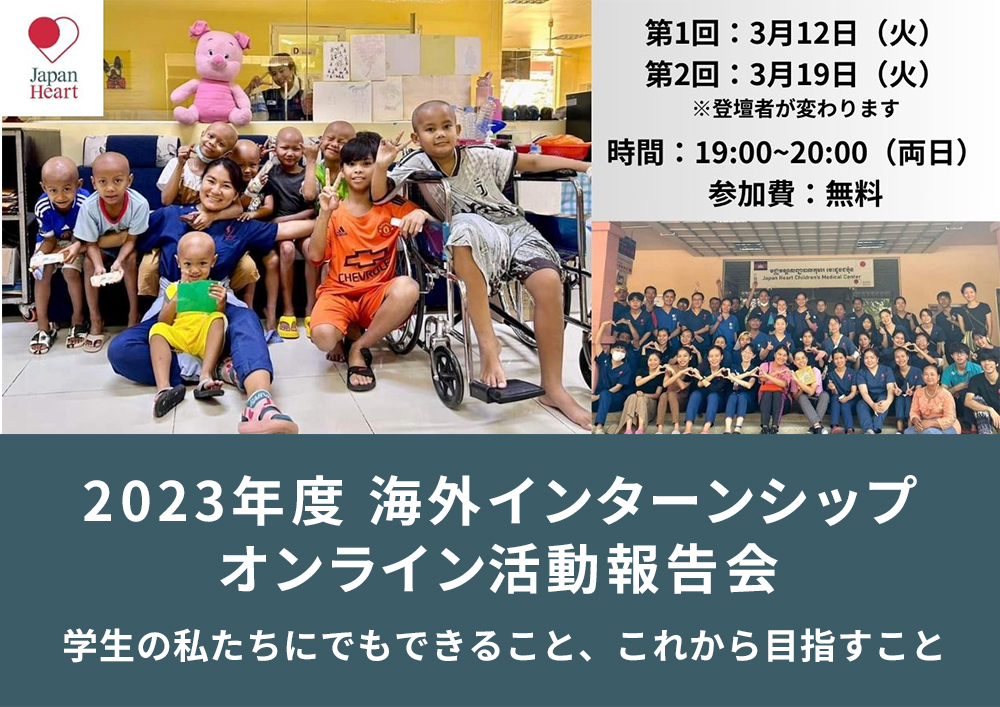
- 03/12 ~ 03/19
- 全国
- 海外インターンシップ活動報告会 ~学生の私たちにでもできること、これから目指すこと~
- 受付中 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 12/26 ~ 03/29
- オンライン
- 【看護師・助産師向け】国際医療 メディカルチーム募集説明会
- 募集中 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 02/03
- オンライン
- 第10回RIKAjob説明会~離島・へき地で最短3か月からの働きのご提案~
- 受付終了 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 03/19 ~ 03/21
- 全国
- 看護師・助産師向け【第4回ナースラウンジ 全国7カ所で開催!!】~国際協力・離島へき地医療の経験のある看護師との座談会~
- 受付終了 More info
- 説明会・体験会
-
- 説明会・体験会

- 02/23 ~ 03/07
- 全国
- 2023年度スマイルスマイルプロジェクト活動報告会のお知らせ
- 受付終了 More info
- 説明会・体験会

